【2025最新版】岸田政権「次の増税」はここだ!所得・消費・資産への影響を徹底予測

🔍 はじめに:なぜ今「増税」が話題なのか
2025年秋、政府与党内で再び「増税論議」が浮上しています。背景にあるのは、少子高齢化に伴う社会保障費の増大、防衛費拡充、そして国債依存体質の改善です。岸田政権はこれまでに企業減税・投資促進を進めてきましたが、その裏で財源の穴埋めとして“新たな負担策”を検討していると見られます。
この記事では、最新の税制調査会や財務省資料をもとに、2026年度までに実施される可能性のある「増税シナリオ」をわかりやすく解説します。
📊 1. 所得税:控除縮小・課税強化の二段構え
所得税の焦点は「控除」と「高所得者課税」の見直しです。政府は2026年度から、給与所得控除・基礎控除の一部縮小を検討しています。特に年収850万円以上の層は、増税効果が顕著になると予測されます。
- 給与所得控除を現行の195万円 → 180万円に縮小
- 高所得者層(年収1,200万円超)に段階的加算税率を適用
- 一方で低所得層には給付的減税を検討
結果として、都市部の中間層(年収700〜900万円)に最も影響が出る見込みです。「サラリーマン増税」というキーワードが再びXでトレンド化する可能性もあります。
🛒 2. 消費税:軽減税率の見直しと“インボイス第2段階”
消費税は表向き「据え置き」とされながらも、実質的な増税となる改正が予定されています。
- 軽減税率制度(8%対象品目)の再検討
- 中小事業者向けインボイス特例(2026年終了予定)の延長なし
- 電子インボイス義務化によるコスト増
これにより、飲食・小売・フリーランスなどの現場に追加負担がかかる可能性が高まっています。特に「免税事業者の排除」が進むと、実質的な消費税増税として受け止められるでしょう。
🏠 3. 資産課税:相続・金融所得に新たな波
政府税調が特に注目しているのが、資産課税の再構築です。富裕層への課税強化を目的に、以下の施策が検討されています。
- 相続税・贈与税の一体化(時価課税導入)
- 金融所得課税の引き上げ(現行20%→25%案)
- 暗号資産・NFTなどの譲渡益課税強化
これらの施策は「格差是正」を旗印に掲げつつも、結果的には中流層の投資・資産形成を圧迫しかねません。
NISAやiDeCoを通じた“資産所得倍増プラン”との整合性も課題です。
💴 4. 家計シミュレーション:どれくらい負担が増える?
| 年収モデル | 現行税負担 | 2026年見込み | 増減額 |
|---|---|---|---|
| 年収500万円 | 約56万円 | 約58万円 | +2万円 |
| 年収800万円 | 約106万円 | 約113万円 | +7万円 |
| 年収1,200万円 | 約178万円 | 約191万円 | +13万円 |
つまり、中間〜高所得層で年間5〜15万円の負担増が現実的なシナリオです。
一方、低所得層には「給付的減税」や「定額補助」が検討されており、階層間格差がさらに広がる可能性があります。
📈 5. 対策:個人が取るべき“防衛策”3選
- NISA・iDeCoのフル活用 — 税制優遇制度を最大限に使い、課税所得を減らす。
- ふるさと納税で控除枠を確実に消化 — 年収800万円なら年間上限約11万円の控除可能。
- クラウド会計ソフトで節税計算を自動化 — 弥生・freee・マネーフォワードなどを利用。
これらは「合法的節税」であり、税制改正後も有効です。特に副業・個人事業主にはAI確定申告ツールが強力な武器になります。
【最新動向】10/14 13:00 更新
- 自民党税調が「高所得者控除縮小案」を議論。
- 公明党との協議は継続中で、結論は年内見込み。
- 株式市場では増税懸念を織り込み、日経平均は一時反落。
🧩 6. まとめ:増税の波をどう乗り切るか
岸田政権が打ち出す「財政再建路線」は避けられない流れです。
ただし、同時に進む減税・補助策をうまく使えば、家計防衛の余地は十分あります。
今後の税制改正議論では、「増税=悪」ではなく、“知って備える”姿勢が求められます。
政治・経済の動向は日々変化します。本記事では今後も税制情報を随時更新し、最新の負担シミュレーションと対策をお届けします。
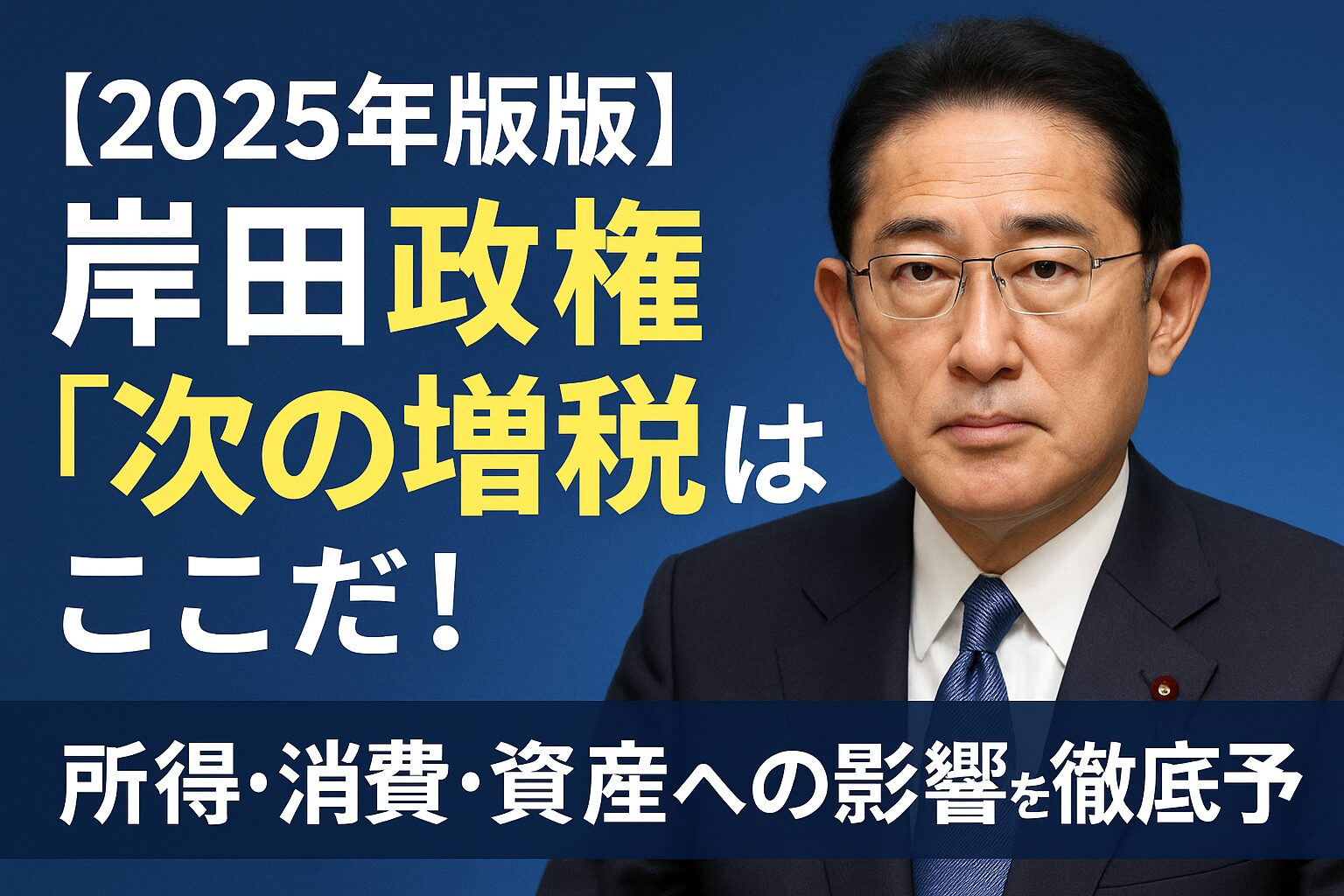


コメント