佐々木朗希|右肩故障から完全復活へ!160キロ連発の裏にあったフォーム修正と美馬学からの学び【ドジャース最新】
右肩のインピンジメント症候群からの長期離脱を経て、9月のリハビリ登板で最速162キロ(平均158.5キロ相当)を計測。フォーム修正の核心と、中継ぎ決断の背景を徹底解説します。
◆ 右肩故障から復帰までの道のり
5月、右肩のインピンジメント症候群(肩峰下インピンジメント)と診断され、負傷者リスト(IL)入り。調整は長期化し、実戦から遠ざかった期間は97日に及びました。8月14日の3A復帰戦以降3試合は球速が伸びず、慎重なリハビリが続きます。
転機は9月9日。5度目のリハビリ登板で、ストレートが一変。最速162キロ、平均も4キロ以上上昇し、ベンチでは笑顔でナインとハイタッチ。結果は5回途中3安打3失点ながら、内容は“復活の兆し”を示すものでした。
◆ “深夜2時の動画研究”が生んだフォーム改善
前夜、空港到着後にホテルで過去の投球動画(大船渡高校時代〜ロッテ時代)を見返したことがすべての出発点。下半身の使い方に「抜け」が生じていると気づき、左足の高い上げ→折り畳み→着地→リリースまでの“力の蓄積と一気の放出”を再インストールしました。
イメージとしては走り幅跳びに近い。助走で勢いを落とさず、踏み切りで最大出力を解放する——この連続性が今季は途中で切れていたという自己分析です。気づきを得た彼は、深夜2時までシャドウピッチングで動作を体に刻み、翌朝のブルペンで球速が2マイル(約3.2キロ)増した手応えを掴みました。
◆ 美馬学の足の使い方から得た復活のヒント
もう一つの鍵は、美馬学投手(楽天→ロッテ)の存在。足をやや高く“巻き込む”ように上げる独特のレッグリフトは、佐々木のリズムと親和性が高い動き。美馬の引退ニュースを機にフォームを重ね合わせ、高校時代に163キロを計測したときの“細身で速い”感覚が鮮明に蘇りました。
ここで重要なのは「真似」ではなく“当てはめ”。自分固有のキネマティクス(運動連鎖)へ、外部の良要素をチューニングして統合すること。これにより、下半身主導の時間軸が整い、上半身の出力をロスなく前方へ伝達できるようになります。
◆ グローブ位置と握りの見直しでロスを削減
プレリリース動作も微修正。従来はお腹の前で握りを作ってから胸元へ上げていましたが、いまは胸の前で握りを決め、即座に投球動作へ。無駄な静止や余計な可動を省くことで、運動連鎖の途切れ(テンポロス)を抑制。回転数の安定と球持ちの改善によって、平均球速の底上げに寄与しました。
◆ ドジャース首脳陣と中継ぎ決断の舞台裏
快投後の9月11日、編成本部長フリードマン氏、GMゴームズ氏と面談。ポストシーズンを見据えた「先発 or 中継ぎ」の選択が提示され、熟考の末に「中継ぎで行きます」と回答しました。来季以降は先発再挑戦が前提。
短期決戦でのローテは通常3人前後。ブルペン強化が勝敗の鍵になるため、160キロ超のフォーシームをリリーバー運用する合理性は高い。本人も「役割を問わず最高の舞台で投げたい」と語り、チーム最優先の決断を下しました。
◆ 妻の合流で私生活も安定、勝負の秋へ
ビザ手続きの関係で渡米が遅れていた妻が合流。プロの調理師による食事設計も受けつつ、「一人でいるのが得意じゃないので安心感がある」と心境を吐露。コンディション維持には、睡眠・栄養・メンタルの安定が不可欠で、私生活の整備は競技パフォーマンスに直結します。
◆ 技術分析:下半身主導と球速回復の相関
1. レッグリフトの“高さ×時間”設計
足を高く上げて畳む動作は、股関節の内外旋と骨盤の回旋を連動させる「溜め」を生みます。ここでのキープ時間が短すぎると、上半身が先行し、球離れが早くなりがち。佐々木は「ふっと力が抜ける」瞬間を排除し、連続性を取り戻しました。
2. テンポ/タイミングの再同期
上肢の外旋ピークと骨盤回旋のピークを同期させると、リリース時のエネルギー伝達効率が上がります。胸前で握りを確定→即動作への流れは、“止めない”=減速しないを徹底する工夫です。
3. 球速だけでなく「平均の底上げ」
最速が戻ることよりも、平均球速の底上げが投球全体の品質を押し上げます。平均158.5キロへ回復した点は、打者のタイミング破壊・空振り率の向上・甘いゾーンでの被打率低下など、複合的メリットに繋がります。
◆ よくある質問(FAQ)
Q1. インピンジメント症候群の痛みは残っていない?
A. 本人は「痛みも不安もない。画像所見も問題なし」とコメント。再発予防として警戒サインの早期察知に努めています。
Q2. なぜ中継ぎを選んだ?
A. ポストシーズンでの登板機会を最大化し、チームに直結する貢献を優先。来季以降の先発復帰が前提で、短期的最適解としての選択です。
Q3. フォーム修正の要点は?
A. 下半身の連続性復元(レッグリフトと骨盤回旋の同期)と、胸前での握り確定→即動作というテンポ設計。これにより平均球速が上がりました。
Q4. 私生活の変化は影響する?
A. 妻の合流で心理的安定が向上。栄養・睡眠のルーティンも整い、長期的パフォーマンスの土台となります。
◆ まとめ:160キロ復活は“原点回帰”の証
深夜の自己対話と美馬学のメカニクスからの着想――この二本柱が、佐々木朗希の剛速球を呼び戻しました。フォームの連続性、テンポ、握りの位置というミクロ調整が、マクロな球速とキレに波及。「最速だけでなく、平均を上げる」という本質的な改良に成功した今、ポストシーズンの高負荷状況での1球に期待が集まります。
◆ 関連記事
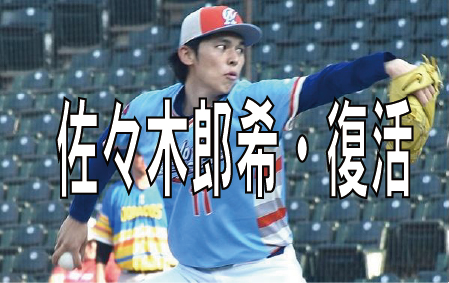


コメント